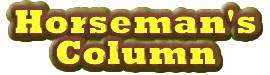|
2025年4月号
 フレームワークとは、馬の姿勢形成のことである。 フレームワークとは、馬の姿勢形成のことである。
馬の姿勢を形成することに、何の意味があるのであろうか。
ライダーが馬上において強制力を発揮できるのは、フレームワークなのである。
フレームワークを簡単な表現をすれば、馬体を曲げることで、ライダーが馬を推進したりその動きをコントロールしたりするには、馬のメンタルなしにできることはなく、物理的に力を行使することはできないのに対して、ライダーの物理的力で、強制的に馬のフレームワークができるのである。
例えば、内方姿勢や屈撓や収縮は、フレームワークの代表的なもので、これらをライダーが、ビットを作用点にしてシートや脚を支点にして、支点やシートを作用点にしたりビット支点にしたりして、馬体を曲げて、内方姿勢や屈撓や収縮を形成することができるのである。
作用点としてレインを真上にピックアップすれば、自動的にシートが支点となり、馬体を左側面から俯瞰すると、馬の頭が真上に向かい、背中が真下に向かう右回転モーメントが発生し、収縮を形成することができるのである。
また、レインを真上にピックアップして、右脚を支点にすれば、垂直方向としては収縮と同じ右回転モーメントが発生すると同時に、水平方向として、ビットが真上に、その反作用として左脚が左方向に力働き、右回転モーメントが生まれて左内方姿勢が形成されるのである。右内方姿勢は、左内方姿勢のとき右脚を支点にしたものを、右脚を支点にすれば、左回転モーメントが生まれるので、右内方姿勢が形成されるのである。
屈撓は、作用点としてビットを真上にピックアップし、両脚を支点にすると、馬の口角とショルダーの間で、左回転モーメントが生まれるので、屈撓することになり、このとき、シートを支点煮れば、馬の口角と後駆の間で右回転モーメントが生まれるので収縮となるのである。
馬のフレームワークは、作用点と支点との組み合わせによって、左右の回転モーメント生じさせるのか、そして、馬体の何処と何処の間で、回転モーメントを生じさせるのかによって、馬体をどのように曲げるかをコントロールできるのである。
 そして、馬のフレームワークは何のために行うかが次の問題で、何のために行うもので、どんな役に立つのかが理解されなければならないのである。 そして、馬のフレームワークは何のために行うかが次の問題で、何のために行うもので、どんな役に立つのかが理解されなければならないのである。
フレームワークの目的は、運動エネルギーの進行方向を馬体の何処から何処へ向かうようするためにあるのである。
例えば、内方姿勢を形成することで、外方後肢と内方前肢が一直線上に位置するので、推進エネルギーが外方後肢から内方前肢へ向かうようにできて、リードのピックアップをし易くなるのである。また、フレークワークの形成が容易になることによって、左右の内方姿勢の切り替えが容易になり、リードチェンジもまた容易にすることができるようになるのである。
更に、フレームワークのもう一つの目的は、重心のコントロールである。
馬の重心は、第4肋骨にあり、バランスフォァの状態が常態なのである。バランスフォァは、直進性は高いが、方向変換は難易性が高いのである。何故なら、体重の配分として前肢に60%、後肢に4%前後になっているために、前肢への負重が多いので、直進性は良く、曲進性は弱いということで、馬術は競馬と違って方向の変換を多用するために、バランスバックし、後駆に重心を移行する必要があり、馬の前駆を高揚させ後駆を押し下げるようなフレークワークをすることで重心を後駆へ移行させて、方向変換を容易にしているのである。
また、レイニングホースのスライディングストップは、バランスフォァの状態ですると、前肢でストップすることとなり、スライディングできないし、前肢の故障にもつながりかねないために、ランダウンのときからバランスバックの状態で走行し、ストップをさせる必要があるのである。そしてまた、スピンで高速回転を可能にするのもまた、バランスバックを要するものなのである。
馬体を左側面から俯瞰すると、バランスフォァの状態の走行は左回転モーメントで、前駆が下がり後駆が持ち上がりながら走行しているのである。一方、バランスバックの所のタイに走行は右回転モーメントで、前駆が待ち上がり後駆が押し下がりながら走行しているのである。
つまり、フレームワークには、二つの目的があって、推進エネルギーの方向に馬体姿勢を沿わせるためや、重心をコントロールのためにあるのである。
|