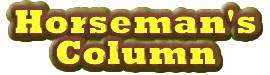|
2025年9月号
 今月のテーマは、乗馬には欠かすことができない馬である。 今月のテーマは、乗馬には欠かすことができない馬である。
馬は、ドメスティックアニマル(家畜)といわれ、サラブレットは3頭のアラビアンホースから生まれたといわれており、アメリカンクォーターホーもまた多くのサラブレッドの血が入っており、日本の在来種は、ポニー程度で馬格が小さく、日露戦争のために陸軍に騎兵隊が生まれて、外来種を輸入したことで、その後の日本の馬が大型化したのである。
ワイルドアニマル(野生動物)の中で、馬科に属する動物は、シマウマとロバだけである。それは、偶蹄目の牛や山羊は蹄が真ん中で割れていて、グランドの起伏に対する対応力が大きいのと比べると、奇蹄目である馬は対応力が小さく、生存率が低いということから現存している動物が少ないといわれているのである。
馬の繁殖に人間が手を尽くしてこなかったら、馬は絶滅していたのではといわれているのである。
因みにアメリカには、クォーターホース協会、ペイントホース協会、パラミノホースブリーダース協会、アパルーサホース協会というように、馬の品種ごとに組織があって、それぞれに、馬の品質の向上にという使命に基づく協会運営が成されているのである。
日本では、競走馬の軽種馬協会、馬事協会があり、乗用馬の品種登録の組織は、馬事協会のみである。従って、品種ごとに競争原理の働きがなく、品質の向上という使命を帯びていないのである。
乗馬社会の制度設計が間違っているのである。
 例えば、自動車社会でも、自動車の販売店で保険を販売しているという現状になっているのである。アメリカでは、とても考えられない社会構造なのである。しかし、誰もこの異常状態を指摘する人はいないのである。 例えば、自動車社会でも、自動車の販売店で保険を販売しているという現状になっているのである。アメリカでは、とても考えられない社会構造なのである。しかし、誰もこの異常状態を指摘する人はいないのである。
何故なら、自動車メーカーは、クォリティーの高い車を格安で販売して利益を上げたいというベクトルを持っているのである。一方保険会社は、安全性の高い車であれば、保険金の支払いが少なくなるので、安全性に高い車を評価するのである。
つまり、保険会社は安全性の高い車を望み、自動車メーカーは安全性より高性能を望むのであり、自動車メーカーと保険会社は利害の反する関係なのである。従って、自動車の販売店が保険を販売することはなく、互いに主張しあって競争するから、消費者はこの恩恵に浴することができるのである。
しかし、日本では、自動車の販売店が保険の販売店でもあるので、競争原理が働かないので、保険会社から自動車の欠陥や安全性の問題で、リコールの事案が出ることが皆無なのである。
社会の競争原理の根本が機能していないために、コロナの案件が発生しても、米問題が発生しても、社会的に冷静な矯正力が機能しなくて、一旦流れができてしまうと、だれにも止められない社会と化して、戦争突入となってしまうのである。
馬は警戒心が強く、人の10倍は緊張しやすいといわれており、集中力の継続時間は、約45分程度であるといわれている。また、視界が広く、後方は馬自身の首が邪魔していている部分以外は大凡見えていて、我々が馬を選択するとき、顔の角に目がある馬を選び、顔の中に目が着いている馬を選ばないのは、視界が狭くなりその分警戒心が強すぎるきらいがあるといわているからなのである。
そして、また、競馬の最高速は、時速65km/H位で、競馬は、1,600m〜2,800m位をレースで走るが、それを全速力で走りきれる馬は存在せず、全速力でコースを走れば死んでしまうのであり、スタミナ配分してレースしているのである。
更にまた、馬は、草食獣で、群れを成し、ボス社会を形成する動物である。
我々人間が馬に騎乗するにおいて、群れを成し、ボス社会を形成していることが重要で、それは、群れを成しボス社会を形成している動物は、その群れに、餌を食べる順番やメスを獲得する優先順などのルールが存在するので、大脳が発達するのである。
そしてまた、馬の運動に特徴があって、それは頭の上下動によって動く動物であることで、このことは人間が馬に乗った大きな要因で、この頭の動きをコントロールすることで、馬の動きを間接的にコントロールできることを、人間が発見して今日人が馬に乗るようになったといわれているのである。
 馬の知能は、地球上にいる動物の上から12番目ぐらいといわれていて、因みに象と犬は4〜5番目ぐらいだそうである。意外に象は、知能が高い動物なのである。 馬の知能は、地球上にいる動物の上から12番目ぐらいといわれていて、因みに象と犬は4〜5番目ぐらいだそうである。意外に象は、知能が高い動物なのである。
日本で馬といえば筋肉のシンボルのように、逞しいものというイメージがあり、馬並という言葉もあるように、食べるのも飲むのも凄い量を食べたり飲んだりするものの例えとしていうのである。
しかし、馬は極力筋肉力を行使せずに動く動物として進化しているのである。
首を伸縮させ頭を上下動し重心移動を行って動いており、重心移動に伴ってステップしているのである。放牧場で馬がリラックスし歩いていると、最初の数歩は肢の筋肉を使っていて、その後は肢の筋肉をほぼ使わずに歩いているのである。
第4肋骨付近に重心があり、前肢に60%、後肢に40%の体重配分で立っているのである。
頭の上下動によって、馬が動いていることを発見した人が、頭の動きをコントロールすれば馬の動きを間接的にコントロールできると考えて、人は馬に乗るようになったのである。
馬の肩から頭までの重量が馬体重の12%前後だといわれていて、この12%の重量を上下動させて、馬の重心移動を促進しているのである。そして、その重心の真上に優れたサドルの鞍壺といわれている部分が存在しているのである。つまり、多少個体差があるが、優れたサドルにシーティングすれば、馬の重心の真上にライダーは、座ることとなるのである。
|