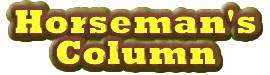|
2025年11月号
今月のテーマは、馬の歩様である。
馬には、4種類の歩様があり、常歩(Walk)・速歩(Trot or Jog)・駈歩(Lope or Canter)・襲歩(Gallop)である。
常歩は、少しだけ速歩より速く常歩をすることができ、速歩は駈歩より少しだけ速く速歩をすることができるのである。このゾーンの常歩や速歩は、常歩は速歩より、速歩は駈歩より体力を消耗するのである。
つまり、馬は速歩より速い常歩をするより速歩で動いた方が楽で、速歩で駈歩より速い速歩をするより駈歩で動いた方が楽なのである。
それにまた、馬は身体の真下に向かって肢が伸びており、この結果、駈歩や襲歩で速く走れるのである。これに比べ鰐は、身体の横に肢が伸びているために、効率よく運動エネルギーを使うことができないので、速歩までしかできないのである。
因みに、鰐が身体の横に肢が伸びているのは、水中では都合がいいのである。
また、運動効率の観点では、脊椎の硬直化した馬は、重心を自在に動かすことができないので、運動エネルギーが重心を通るように進化していて、それは、馬体の対角線上を運動エネルギーが通るように、馬は、斜対速歩であり、斜対駈歩であることで明らかなのである。
常歩(Walk)

常歩は、4拍子で、4肢が同時に宙に浮くことはない歩様で、常歩で動いているとき、必ず4肢のどれかがグランドについているのである。
(1)左後肢 (2)左前肢 (3)右後肢 (4)右前肢 または、(1)右後肢 (2)右前肢 (3)左後肢 (4)左前肢の順で動いているのである。
このとき、馬の頭は、左後ろに上がり左前に下がり、右後ろに上がり右前に下がることを繰り返す場合と、右後ろに上がり右前に下がり、左後ろに上がり左前に下がることを繰り返しているのである。
速歩(Trot or Jog)

速歩は、2拍子で、馬体の対角線上の肢が同時にステップしている歩様で、(1)左後肢と右前肢 (2)右後肢と左前肢、または、(3)右後肢と左前肢 (4)左後肢と右前肢という順でステップしており、(1)と(2)の間に、馬体は宙に浮くのである。
駈歩(Lope or Canter)

駈歩は、3拍子で、リード(手前)があり、左リードは、(1)右後肢 (2)右前肢と左後肢 (3)左前肢、右リードは、(1)左後肢 (2)左前肢と右後肢 (3)右前肢の順でステップし、(3)から(1)へ移行するときに馬体が宙に浮くのである。
襲歩(Gallop)

襲歩は、4拍子で、左リードは、(1)右後肢 (2)左後肢 (3)右前肢 (4)左前肢、右リードは、(1)左後肢 (2)右後肢 (3)左前肢 (4)右前肢の順でステップし、(2)から(3)へ移行するときに馬体が宙に浮くのである。
馬は、常歩から駈歩までは、ほぼ同時に獲得したといわれており、その理由は、速歩において、馬体の対角線上の前肢と後肢が同時にステップしているが、厳密には前肢が速く着地していて、それは常歩と同じステップの順になるのである。
また、駈歩は、(2)で前肢と後肢が一緒にステップしているが、これも厳密には前肢が速く着地していて、それは常歩と同じステップの順になるのである。
従って、馬は、常歩から駈歩までは、常歩と同じステップをしており、前肢と後肢が同時に着地しているので、馬体の長さ以上にストライド(歩幅)を大きくすることはできないのである。
襲歩は、常歩から駈歩までとは全く違う歩様で、常歩から駈歩までを獲得してから相当の時間経過があって獲得したのではないかといわれているのである。
そしてまた、後肢と前肢の着地の間に馬体が宙に浮いているので、馬体の長さ以上にストライドを大きくできるのである。
因みに、馬が速く走るためには、ピッチ(肢の回転)を速くする、またはストライドを大きくしているのである。
|